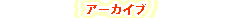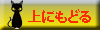『医学常識はウソだらけ』
物理学者・三石巌氏は、還暦の年、目がひどくかすむので大学病院の眼科に行ったところ、白内障で2-3年すれば目が見えなくなると断言される。そこで自分で治してやろうと決意し、理論的思考によって着目したのが「栄養」。白内障の原因はビタミンCの不足だとある。けれども、何十年と同じ食事をし、同じ量のビタミンを摂っているはずの奥さんは、白内障にかからなかった。それは何故か。自分の眼球が他の人より余計にビタミンCを必要としているからではないか。それが不足していたから、眼球がダメージを受けたのだ。だとすると、これから浴びるほどビタミンCを摂取していけば、白内障の進行を食い止められる。少なくとも、完全な失明は避けられる可能性が高い。この仮説にしたがって、ビタミンを注射し、その結果は、言うまでもなく、原稿を執筆し、細かい譜面をみながらパイプオルガンも演奏。2-3年で見えなくなるはずだった目は、35年たっても、本来の役目を果たしてきた。
分子生物学に基づいた分子栄養学(三石理論)を提唱。ご自身の健康管理を実践し、95歳の天寿を全うする。以下、知っていればためになる、分子栄養学・三石理論の抜粋です。
点滴が原因で重度の記憶喪失に
医療過誤が原因で、ウェルニッケ脳症になった男性。胃の手術をした後、高カロリー輸液を点滴で受ける。ところが医者が輸液に必要なビタミンを入れなかったため、術後2か月で発症してしまう。(編集部注・平成9年4月15日付朝日新聞夕刊に、点滴を受けた患者がウエルニッケ脳症になる医療事故が後を絶たないという記事が掲載される。医者の認識不足のために、必要なビタミンB1が同時に投与されなかったことが原因としている。)
「食塩を摂りすぎると高血圧になる」のウソ
食塩に含まれるナトリウムは、体内に水分を保持させる働きをする。その濃度が高くなると体液が増え、その結果、血管を通る血液の量も増えて血圧が高くなるのは事実である。しかし高血圧の原因はそれだけではない。東北地方でもリンゴの生産地では高血圧が少なかった。リンゴを沢山食べている人が高血圧になりにくいことは、栄養学的にも裏付けられる。血圧を平常に保つためには、ナトリウムとカリウムの比率が重要。
カリウムは、リンゴ、メロン、スイカ、バナナといった果物や野菜などに多く含まれている。食塩を平均より多く摂取するといわれる地域でも、リンゴを日常的によく食べる地域では高血圧が少なかったのはこれで説明がつく。高血圧の一つの原因は、食塩の過剰摂取ではなく、カリウムの不足といった方が正しい。高血圧には、まず良質のタンパク質が不可欠
血圧のコントロールにはカルシウムとマグネシウムの摂取比も大切。動脈の収縮にカルシウム、弛緩にマグネシウムが関わっており、マグネシウムは高血圧や不整脈を予防することがわかっている。血管の弾力性を保つためには、血管を作る材料としての良質タンパクをきちんと摂取しなければならない。
血圧降下剤は血栓を惹き起こす
手っ取り早く血圧を下げるには、利尿剤によって尿の排泄量を増やしてやり、体内の水分を外に出して血液量を減らせばいい。だが、血液は水分だけで成り立っているわけではなく、その中には、様々な物質が含まれている。利尿剤によって減るのは水分だけなので、煮詰まった味噌汁みたいなもので、濃度が高くなっており、粘り気が増してゆく。血液は、粘度が高いほど血栓を起こしやすい。利尿剤の副作用として脳血栓を起こすケースが多いのは、そのためである。
高血圧は栄養改善で治すのが一番
それ以外の血圧降下剤も副作用があるという点では似たようなものである。脳に影響を与えてうつ病を起こしたり、無気力になる人もいる。問題の本質はカルシウムの摂取量である。血圧をコントロールするためには、カルシウムとマグネシウムの比率適正を保つことが大切である。食品から摂取する栄養をきちんと管理していれば、薬に頼る必要はない。『正しいミネラルバランスが血圧を正常にする』をクリック。
コレステロールは、本来”健康の味方”である
脂質の一種であるコレステロールも、細胞を作るときに必要な材料の一つである。すべての細胞は細胞膜に包まれている。その細胞膜を作る成分として、コレステロールはきわめて重要な存在である。この材料が不足していると、新しい細胞を正しく作ることができなくなってしまう。コレステロール不足がガンを招きやすいといわれるのもそのためで、細胞膜が弱いとその部分がガン化しやすいわけである。
また、皮膚にあるコレステロールは紫外線を浴びるとビタミンDの前駆体になる。ビタミンDは、とくにカルシウムの吸収に必要とされる物質である。したがって、コレステロールが少ない人はビタミンDが不足し、その結果、カルシウムの吸収が不十分になって骨が弱くなってしまう恐れがある。
コレステロールは、肝臓でリボタンパクというタンパク質に包まれ、梱包された状態で血液の中を流れて、必要なところに届けられる。パッケージにはいくつか種類があり、問題にされるのが俗に「善玉コレステロール」と呼ばれるHDLと、「悪玉コレステロール」と呼ばれるLDLであり、コレステロールそのものの種類ではなく、コレステロールを梱包したパッケージのこと。
LDLが肝臓から発送されてコレステロールを必要とする組織へ運ぶのに対し、HDLはたとえば、血管壁などで余ったコレステロールがあると、それを元の肝臓へ持って帰る役割を担っている。往路のLDLにはコレステロールが多いが、復路のHDLには少なく、代わりにレシチンが多い。コレステロールを目の敵にするのは、動脈硬化や心臓病などの促進因子という考え方からだが、LDLに対して、HDLの割合が多ければ問題は生じない。