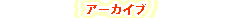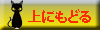インテリジェンス
エッセイ・随筆
ノンフィクション
ミステリー
医療・健康
大学病院のウラは墓場
廃用身
破裂(上)(下)
人がガンになるたった2つの条件
人殺し医療
医者に寿命を縮められてはいけない
医学常識はウソだらけ
神の手(上)(下)
「きれい好き」が免疫力を落とす
まず石を投げよ
モーツアルトとレクター博士の医学講座
炭水化物が人類を滅ぼす
「余命3ヶ月」のウソ
政治・外交
哲学・宗教
歴史・地理

『海賊とよばれた男(上)』 百田(ひゃくた)尚樹著作。図書館で借りるのに10か月程待つ。著者・百田氏は、1953年に起きた「日章丸事件」を調べ、その全貌を知るにつれ、「現代の日本人が忘れかけている『勇気』『誇り』『闘志』そして『義』の心を持った男たち、そしてそんな男たちを率いた一人の気骨ある経営者の姿を書きたい!いや、書かねばならない!」と思う。出光興産の創設者・出光佐三がモデル。明治生まれの気骨ある、自らが正しいと思ったことは決して曲げない生き方を貫いた人物が描かれており、誇り高き、立派な日本人がいたことに強く感銘を受ける。上巻は、第一章「朱夏」(昭和20年~22年)、並びに第二章「青春」(明治18年~昭和20年)から成る。終戦直後、殆どの資産を失って倒産寸前となり、仕事が全くなくなっても、「社員は会社の財産である」と、社員の首を切ろうとしなかった。現在の経営者たちとは、対極の考え方である。自分たちの利益ばかりを追求するのではなく、世の為、人の為にことを成す。 第二章「青春」を読んでいる時は、まるで激動の昭和を体験しているようで、陸軍の暴走を肌に感じる。石炭が主流だった時、既に石油の時代が来ることを予測する先見の明。不可能だと言われることに立ち向かい、可能にする勇気と行動力。法律がこうだからダメと言われても、「法律とは人々の暮らしをよくするためではなかとですか」と、本質をつく。下巻の予約を申込済みだけれど、この受取もかなり待たされそう。 (講談社文庫)

『ザ・ロスチャイルド』 渋井 真帆著作。「第4回城山経済小説大賞」受賞。英国ロスチャイルド家を起こしたネイサン・マイヤー・ロスチャイルドに焦点をあてた歴史小説。フランス兵に捕まり、処刑寸前に、命を救ってくれた青い目の覆面の人物(これって実話?)はいったい誰なのか?恋人エルザを亡くし、ナポレオンへの復讐を誓うネイサン。翻訳文のような文章が気になったけれど、ストーリの運び方が面白い。ロスチャイルド家は如何にして巨万の富を築き、世界の大富豪となりえたのか。顧客の富を、それが不正なものであっても、積極的に資産管理し、お金を稼ぐ。5人兄弟の団結と協調、素早い情報の獲得、そして金を安い市場で買っては、高い市場で売りさばき、その繰り返しによって、利益を蓄積。大陸封鎖という困難な壁を、知恵を使い、創意と勇気でもって打ち破り、ナポレオンとの兵站戦争に勝つ。投機ブームの作られ方とその結末、売り注文と買い注文を作りだし金融市場を操作する「突き落として、空高く上昇させる」やり方。あの投機家・村上世彰を連想する。数多くのノーベル賞受賞者を出し、今なお金融界を君臨するユダヤ人たちだが、何故昔からユダヤ人は忌み嫌われてきたのだろうか?と、ずっと不思議であった。”稀代の英雄”と言われたナポレオンは、家族思いの母親を大切にする人だった。この本の中でも、やさしい気配りをする”英雄”ナポレオンがいる。 (ダイヤモンド社)

『竜馬がゆく(1)~(8)』 司馬 遼太郎著作。むかし随分夢中になって司馬作品を読んだものだが、『竜馬がゆく』、『飛ぶが如く』は読み切るのに体力と時間を要するボリュームなので、いつかそのうちと、読み残していた。今回、高知にご縁があり、いろいろ調べていると、「土佐北街道」がよく出てくる。竜馬もこの道を歩いたのだろうかと、しきりに竜馬が頭に浮かぶ。さあ、今が読み時と、図書館で本を借りてきた。文庫本8巻(単行本5巻)読むのはさすがに疲れる。このひと月程は、頭の中は幕末時代にあった。今まで点でしか把握できていなかった歴史的事実が、線でつながり、立体的に動き出し、司馬氏の幕末感、竜馬像にしばし魅了される。著者は、「竜馬を通して、幕末の青春像を書こうと思った。日本史が所有している”青春”のなかで、世界のどの民族の前に出しても十分に共感をよぶに足る青春は、坂本竜馬のそれしかないという気持ちで書いた」という。一つの枠にとらわれることのない独創的な思考。常識では考えられない大胆な行動。「これほどあかるく、これほど陽気で、これほど人に好かれる人物は少ない。」あれほど犬猿の中の薩摩と長州の、絶対不可能と思われた「薩長連合」を遂げ、戦争によらずして革命を遂げるための「大政奉還」へと導き、革命後の明確な新日本像を「船中八策」として打ち出した竜馬。「天がこの奇跡的人物を恵まなかったならば、歴史は変わっていたのではないか」 (1962/6/21~1966/5/19 産経新聞夕刊に連載)(文春文庫)

『まず石を投げよ』 久坂部 羊著作。タイトルを見たとき、すぐ頭に思い浮かんだのは聖書に出てくるパリサイ人の石打の話。医療ミスがテーマである。医療ミスに直面した時、医師はどのように振る舞うか、医療界の隠蔽体質を実証するため、にせの医療ミスを演出し、医師を試す。マスコミの行き過ぎた許されざる行為だが、彼らは使命感に燃えていて、気づかない。実験された医師は自殺。宍村は、はじめて自分の心の動きも医療ミスを犯した医師と同じであったことに気づく。ここで初めて何故このタイトルが付けられたのかを理解。宍村は、相手に石を投げ、そして自分にも石を投げる。久坂部氏の小説の主人公は、いつも心の中に苦悩を抱えた、虚無的な複雑な心の持ち主が多い。三木医師然り。私は、余り深くこの聖書の話を考えたことがなかったのだけれど、キリストは人を罰することを求めていない。人間は過ちを犯すもの。過去を振り返ると、反省すべきことの何と多いことか!自分も他人も許しましょう。 (朝日新聞出版)

『地図のない道』 須賀 敦子著作。福岡伸一氏のお薦めの書で、「この本を片手に街を歩く」とのこと。彼女のエッセイを読んでみたくなる。初めて彼女の作品に触れたのが14~5年前。既に彼女は亡くなっていた。『1943年、10月16日』という歴史書のような本をイタリアの友人が贈ってきたことから、このエッセイは始まる。ローマのゲットーへユダヤ料理を食べに行ったこと、ルチアという友人の案内でベネツイアに行ったこと、そして後日、〝ルチアのあの橋”が〝グリエ“という名前の橋であり、その周辺はベネツイアのゲットーであったことを知る。ルチアはユダヤ人だったのか?両親はいないといった彼女。1943年10月16日、ローマがナチの軍隊に占領され、ゲットーのユダヤ人はナチ収容所に連行された。彼女はそれと関係があったのでは?「ザッテレの川岸」で、〝リオ・デリ・インクラビリ”(治る見込みのない人達の橋)という衝撃的な名前を見つける。”治る見込みのない人たちの病院”があったから、その名前がついた。突然、修道院のような建物の映像が、タイムスリップしたかのように、私の記憶に浮かび上がる。この光景って、昔テレビで放映されたよね!昔見た映像のエッセイと「地図のない道」に綴られたベネツイアの姿が重なる。ベネツイアと言えば、ルキノ・ビスコンティの名作「ベニスに死す」の主人公の迷路のような道をさまよい歩く姿が思い浮かぶ。 (新潮社)
2006年11月、「イタリアへ...須賀敦子 静かなる魂の旅 第1話」がBS朝日で初回放送されている。


『神の手(上)(下)』 久坂部 羊著作。プロローグに出てくる”センセイ”とは誰?ファーストクラスに乗り、医療事情や薬に精通し、元総理を前に堂々と持論を述べることのできる人物。どう考えてもカリスマ性のある医師としか思えないのだが。それから12年の歳月が流れ....、物語が始まる。安楽死法制定を巡って、次々と人が死に、結末は不自然すぎて、これはミステリー小説に分類すべきと思うのだが。現在の日本の医療についての問題点が分かりやすく描かれており、また「安楽死法」を巡って、患者と向き合った医者の立場、利権を追い求める権力志向者の立場、そして官僚の発想等が、いろいろな角度から語られる。「人の命を奪う安楽死は、聖なる神の営為です。すなわち安楽死を執り行う医師は、”神の手”を預託された存在なのです」と安楽死を美化して語る人物。しかし、安楽死といっても人を殺すことなのだと、久坂部哲学は語る。 (幻冬舎)

『大学病院のウラは墓場』 久坂部 羊著作。大学病院は医療の最高峰であり、治療は難しいが治る見込みのある患者のみ対象。初めから十分な経験のある医師などいるはずがなく、患者を練習台にするのは誰でもやっていること。日本の大学病院には医局があり、国公立の総合病院は、殆どが医局の関連病院である。2004年、新しい臨床研修制度で研修医が自由に病院を選べるようになると、都市部の病院に人気が集中。地方医師の不足が起き、人口過疎地では医療が成り立たなくなった。勤務の厳しい訴訟リスクの高い、産科、小児科では医師不足が起き、外科もなり手が減少している。日本の医療は今急速に破綻に向かっている。旧弊な医局制度が破綻し、医師は自由を得た代わりに安定と将来の保障を失い、世間は地域医療と産科医と小児科医を失った。患者は医療訴訟で権利が守られるようになった代わりに、訴訟のリスクの高い科の医師を失いつつある。今日本で起きている医療危機は、人間に自由を与えすぎると、社会がダメになる一つの典型であると。 (幻冬舎)

『炭水化物が人類を滅ぼす』 夏井 睦(まこと)著作。図書館で借りてくるのに、5か月程予約待ちし、ようやく読むことのできた人気の話題作。著者自身、インターネットで江部康二氏(京都高尾病院)の記事を読み、ものは試しとご飯の量を減らしてみた。糖質制限開始から5か月ほどで、体重が11キロ減った、から揚げもフライも以前より沢山食べていたのに高血圧も高脂血症も自然に治っていた、昼食後に居眠りしなくなった、飲酒量は減らしていないのに二日酔いしなくなった等々、ご自身の体験から、炭水化物を制限すれば殆どの病気を予防できるのではないかとし、「高タンパク質、高脂質、糖質ゼロ」の食事を推奨。細胞を作るのに必要な栄養素は、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラルであり、糖質(炭水化物)は血糖値を上げるだけのもの。糖尿病の根本的治療には、薬もインスリンも不要な「糖質制限」をすればよい。脳に必要なブドウ糖は、アミノ酸を材料に作られるため、炭水化物から摂取する必要はない。食事で外部から取り入れるべき必須脂肪酸、必須アミノ酸はあるが、必須炭水化物は存在しない。牛は何故草だけ食べて生きていけるのか等々、話しが面白く、自分の食生活を改めて考えてみるのに参考になる書。 (光文社)

『大使館なんかいらない』 久家(くげ)義之著作。2001年3月初版発行。2003年、小説家として本格デビューする以前に書かれた久坂部羊氏の著作の一つ。1988年~1997年の約9年間、外務省医務官として、サウジアラビア、オーストリア、パプアニューギニアの三か国にて勤務。また、出張や会議で30程の日本大使館や日本総領事館を見てきた。彼独自の鋭い観察眼で見た大使館の驚愕すべき実態とは。外交なら機密費が必要という幻影のもと、割り当てられた多額の報償費は、大半が諜報のシロウトである大使館員によって極めて効率悪く使われている。日本は何故シロウトみたいな開発援助(ODA)をするのか。発展途上国の援助をしたいのではなく、外務省の国際社会に向けてのスタンドプレイ・実績誇示が目的だから。サウジアラビア大使館では、毎朝、新聞会議があり、新聞から情報を得ていた。これは平時の偽装で、本当の諜報組織は大使館の中枢に隠されているのかと思ったが、そんなものがないことは、1990年夏に勃発した湾岸危機ではっきりした。1996年12月18日に起きたペルー大使公邸人質事件。その国のVIPを一堂に招くナショナル・デーのレセプションで、ゲリラの襲撃を許し、人質を取られ、公邸を占拠されるという、日本の甘い危機管理が露呈し、世界に大恥をさらした。「この国際化時代に『外交』はますます重要だが、『外務省』が必要かどうかはまた別問題である。この本のタイトルは少し言い過ぎかもしれないが、大使館の在り方を再考するために敢えてつけた」と、言う。元外交官の佐藤優氏は、幾多の著作の中で、外務省巨額機密費の横領・着服事件をはじめ、伏魔殿(名付け親は田中真紀子氏)外務省の様々な魑魅魍魎を語っている。外務省の非・常識を初めて知ったのは佐藤氏の著作にて。 (幻冬舎)

『廃用身』 久坂部羊著作。2003年、この作品にて作家デビュー。冒頭に、「*プライバシー保護の為、年齢や病名は内容を損なわない程度に事実を変えてあります。*本書に登場するお年寄りは一部実名で書いています。.....」と、記されている。また、現実の老人問題が実に生き生きと描かれているため、これってノンフィクションなのかと思いつつ読み進む。神戸山手に開設した老人デイケアに尽力する「異人坂クリニック」の院長・漆原糾医師が、自ら考案した「Aケア」について書き残した遺稿『廃用身』が前半部。後半部は、『編集部注 ― 封印された「Aケア」とは何だったのか』(矢倉俊太郎)。奥付けには、両名の著者略歴が書かれている。二人の著作で構成されたノンフィクション作品だったのか。何故、久坂部氏の名前がないんだ?更にページを繰ると、著者名・久坂部羊の奥付け現る。やはり架空の小説だったんだ!それにしても手の込んでること。「Aケア」とは〝廃用身”の切断(amputation)を介護の一環として行うケアのこと。Aは切断(amputation)のA。〝廃用身”とは、医学用語の「廃用肢」のことで、脳梗塞などの麻痺で回復の見込みのない手足のこと。頭まで含むとなると怖すぎる。〝廃用身”の切断療法による効果が、明晰に論理的に語られていて、自然に反する過激なやり方だけれど、説得力がある。事実をよく検証せず、自分たちに都合のいい発言だけを歪曲して採り上げる、そんなマスコミ情報もあるということを心しておかなければ。 (幻冬舎文庫)

『破裂(上)(下)』 久坂部羊著作。阪大医学部がモデルとなった小説として、①『白い巨塔』(山崎豊子)、②『きりひと賛歌』(手塚治虫)、そしてこの③『破裂』があげられる。「医者は3人殺して一人前」と書かれたこの本の帯を見て、当時の阪大病院長は、「これは名誉棄損や!誰がどう読んでも阪大病院のことやないか。訴えてやる!」と、激怒した。「どうぞ訴えて下さい。その方が本が売れるから」と、久坂部氏の渋い答え。本に一杯付箋を貼って「ここと、ここと、ここがけしからん」って、かなり頑張っていた病院長は、急に腰砕けになってしまった、というエピソード付きの小説がこれ。
医療ミスの真相を求めて起こされた裁判。日本の高齢社会の問題解決として、厚労省のマキャベリとあだ名される佐久間の考える”プロジェクト天寿”(超高齢者の人為的ポックリ抹殺計画)。この二つを軸に、屈折した正義漢である麻酔科医江崎、医療ミスを頑なに追及しようとするジャーナリスト松野、次期教授の椅子を狙う心臓外科医香村、そして厚労省のマキャベリこと佐久間、等々の個性的な人物が複雑に絡み合って物語が展開。知らない医療の世界を知る面白さ。想像もしなかった官僚の実態を違った角度から眺める面白さ。久坂部氏の描く世界は、面白くて目が離せない。 (幻冬舎文庫)

『モーツアルトとレクター博士の医学講座』 久坂部羊著作。作家、医師、そして三足目のワラジとして福祉系の大学で「医学概論」を講義。その講義ノートの一部を読み物風にアレンジしたものがこれ。「一つ目小僧」はありえるが、「三つ目小僧」はあり得ないその理由。ヘビースモーカーの肺はコールタールのような汚れがべっとりこびりつき、気管支を切ると断面からタール状のニコチンが垂れてくる。認知症には有効な薬はなく、症状の進行を抑制すると言われるが実際のところ分からない。鳥は何故夜には物が見えにくいのか、等々、医学的観点から面白可笑しく説明されている。 (講談社)

『ブラック・ジャックは遠かった 阪大医学生ふらふら青春記』 久坂部羊著作。一浪の末に名門・大阪大学医学部に入学した著者。浪人時代の猛勉強の反動からか、授業をサボり、サッカー、合コン、飲み会、スキー、一人旅と、半端でなく遊んでいた中之島青春時代。本は読まずとも、小説家になれることを信じ、授業をさぼって執筆活動。それから20数年後、医師として働きながらも小説家としてデビューし、初志貫徹。何事にもひるむ事なく立ち向かうその行動力、物おじしないその勇気。メチャメチャ面白い。 (140B出版)

『悪医』 久坂部羊著作。大阪大学医学部卒業の医師・作家。2014年、第3回日本医療大賞を受賞。がん治療の拠点病院にて、「これ以上、治療法はない。残された時間を有意義に使って下さい」と、医師から余命を宣告された末期がん患者。医者に見離されたと憤り、何が何でも治してみせると、大学病院⇒腫瘍内科病院⇒がん免疫細胞療法専門クリニックと治療を求めて病院を転々。最後にがん患者への精神的支援をする組織に出会い、ホスピスにて痛みや苦痛を抑える治療を受け、穏やかに死を迎える。一方、治療法がないと告知した医者は、末期がん患者に対してどう対応すべきかと思い悩む。がん治療法やそれに携わる医者の実態が描かれている。「抗がん剤ではがんが治らないという事実を殆どの医師が口にしない」のは何故か。 (朝日新聞出版)

『「余命3ヶ月」のウソ』 近藤誠著作。「がんが恐ろしいのではない。”がんの治療”が恐ろしいのです」、「余命3ヶ月?いま元気なら、すぐには死にません。がんの治療で余命3ヶ月に」、「固形がん(肺がん、食道がん、胃がん、肝臓がん、乳がん、大腸がん等のこと。睾丸がん、子宮絨毛がんは除く)には、抗がん剤は効かない」、「健診は百害あって、一利なし」、「がんは原則として放置した方がいい」等々の近藤理論が満載。がんには、「本物のがん」と「がんもどき」があり、「本物のがん」は早期発見時点であっても、既に転移している為、手術や抗がん剤治療をしても無駄、苦しむだけである。「がんもどき」は、転移しないがんであり、自然に治る。欧米では「がんもどき」はがんと見なさず、がんの定義が日本と異なる。がん検診は日本でだけ盛ん。(KKベストセラーズ)

『医者に寿命を縮められてはいけない』 石原結實著作。 石原式健康食「朝はニンジン・リンゴジュース、昼は蕎麦、夜は好きなものを食べる」を推奨。東洋医学を見直して、自然治癒力を高めよう。体を温め、食べ過ぎないで、免疫力をつけ、「元気になろう」「病気を治そう」。目から鱗の情報が簡潔に書かれ、健康管理のための必読の書。 (三笠書房)

『人がガンになるたった2つの条件』 安保徹著作。何故ガン細胞は、「低体温」「低酸素」が好きなのか。人間の60兆個の細胞1つ1つが、何故「無酸素で成り立つ解糖系」と「酸素を使って効率的にエネルギーを作り出すミトコンドリア系」の2つのエネルギー製造システムを持っているのか。38億年前の生命誕生、光合成による酸素の発生、そして2つの生命の融合現象。ガン細胞とは何か?複雑な細胞のしくみが分かりやすく説明されていて、まるで大学で講義を受けているかのようだ。 (講談社+α文庫)

『「困った隣人・韓国の急所』 井沢元彦/呉善花著作。李氏朝鮮時代、仏教や儒教の別派を排除し朱子学一本で国家国民の全体を統括する。朱子学は朝鮮半島で強化され、完成された。自己中心的で他の文化を認めない朱子学。李承晩ライン・竹島占拠は、韓国の対日姿勢を決定づけた最大の国家戦略。朝鮮における日本統治時代の真の姿はどうだったのか。韓国の歴史認識は、真実とかなり異なるのでは。 (祥伝社新書)

『「きれい好き」が免疫力を落とす』 藤田紘一郎著作。抗菌グッズ大好きな「きれい好き」日本人に何故アレルギー体質が増えているのか?回虫博士・藤田氏が、何でもかんでも殺菌、消毒と、きれい好き過ぎて免疫力を落としている現代の日本人の注意すべき点を説明。 (講談社)

『人殺し医療―マフィアが支配する現代メディカル・システム』 ベンジャミン・フルフォード著作。大麻やケシは万能薬である。ロックフェラーが「大麻」販売権を独占。ビタミンDはインフルエンザ感染予防としてワクチンの5倍の効力がある。インフルエンザは毎年変異。新規にワクチンを製造しても、基本的に効果なし。むしろ副作用がかなり強い。集団接種による注射針の使い回しにより肝炎ウィルスに感染した人が多い。風邪のように寝ていれば治る病気でも、薬を処方。下手に解熱剤を呑めば、ウィルスが体内に残り、残ったウィルスが肺や脳で再繁殖し、急性肺炎や急性脳炎で命にかかわる。健康診断による医療被曝が日本人にガンを惹き起こしている。現在の西洋医学オンリーの医療体制から、江戸時代のように西洋医学、漢方医学、針・灸・あん摩の民間療法等を含めたバランスの良い総合的な医療体制に変えるべきで、「完治」ではなく、「養生」を目指せ.....等々、自分の命は自分で守らなければ。 (KKベストセラーズ/¥1,575)

『地獄の季節・「酒鬼薔薇聖斗」がいた場所』 高山文彦著作。1997年5月27日、神戸市須磨区の友が丘中学校の正門前に土師淳君の頭部が発見された。その犯人〝酒鬼薔薇聖斗”の育った須磨ニュータウンに焦点をあてて、少年Aが描かれ、彼の心の叫びが聞こえてくる。著者が少年Aと同じ中学3年になったばかりのとき、偶然手にしたランボーの『地獄の季節』によって、著者は救われた。自分自身のかっての嵐のような衝動を思い起こし、少年Aの心の風景を描く。少年の血のルーツである沖永良部島に足を運び、近代都市神戸と南島の風がせめぎ合う気配を感じる。人間臭さの皆無な街、ニュータウン。感受性の強い少年Aの心の奥深くにあったものとは。歯車はどこで狂い始めたのだろう。 (新潮文庫/¥552+税)

『「少年A」・14歳の肖像』 高山文彦著作。『地獄の季節・「酒鬼薔薇聖斗」がいた場所』に続き、同じ著者により、少年Aとその彼の育った家庭に焦点をあてて描かれる。目に映ったものを形から色、数まで克明にありのままに記憶してしまう「直観像素質」の才能があり、人並み外れて記憶力がよく、幼少期のダリと奇妙な程一致する点があった。だが、美術が得意だった彼の才能を存分に発揮させてやる環境ではなかった。母親は、幼少の頃から厳しく少年を叱って育て、躾けのつもりで手厳しい折檻を加えていた。少年の避難場所は、祖母であり、両親をまったく信頼していなかった彼にとって、祖母は唯一心を許す存在であった。そして、祖母の死。死とは一体何なのかと疑問を持ち始める。 (新潮文庫/¥400+税)

『毒婦 木嶋佳苗 100日裁判傍聴記』 北原みのり著作。2012年1月10日に始まり100日に及んだ木嶋佳苗裁判の傍聴記。木嶋佳苗、逮捕当時34歳。ネットで知り合った男たちからは、結婚をちらつかせ、多額のお金(一億円以上)を貢がせた。周囲の男たちは次々と不審死。亡くなった男たちは、皆、佳苗に恋をしていた。そして、睡眠薬を飲み、練炭が焚かれる中、眠るように逝っている。ある男は非常に穏やかで口元に笑みを浮かべて。あの容姿でどうして男たちを次々騙せたのだろう。佳苗にとって、男とは何なのだろう。18歳で北海道から上京してきた34歳の女に、この世界はどう見えたのだろう。 (朝日新聞出版/Y1,200+税)

『別海から来た女』 佐野眞一著作。男性目線で描かれた木嶋佳苗の「睡眠薬と練炭を使った首都圏連続不審死事件」について。第一部では、木嶋家のルーツや木嶋の故郷の別海町の関係者の話。第二部の傍聴記では、裁判で明らかになった事実が、佐野氏の詳しい調査を加え、描かれている。「木嶋佳苗という女の『悪の輝き』は百日裁判の法廷でのやりとりの中に最も底光りしており、その質疑応答の中にこそ、木嶋佳苗に翻弄された男たちの愚かさも滑稽さもまた色濃くにじみ出ている」とする。ウソつき佳苗の次から次と嘘で塗り固めた話に苛立ちを感じ、淡々とは受け止められないようだ。 (講談社/Y1,500+税)

『ウルトラ・ダラー』 手嶋龍一著作。場所は、京都馬町の旧小林古径邸、浮世絵オークション会場。主人公・英国の諜報員でBBC日本特派員スティーブンが、”ダブリンに新種の偽百ドル札「ウルトラ・ダラー」あらわる”のメッセージを受けとる。舞台は、30数年前に遡り、1968年12月、東京下町で若い彫刻職人が忽然と姿を消す。「北」によるウルトラ・ダラー製造の動機は何か。核弾頭を運ぶ長距離ミサイルを手にする資金にしようとする北朝鮮は、北京の単なる駒にすぎないのか。アジア大洋州局長の実母が朝鮮国籍の工作員であったという驚愕の”フィクション”あり、どこまでが真実で、どこからが虚構なのか。拉致問題の真相とは。中国とはいかなる国であるのか。 (新潮社/¥1,500)

『スギハラ・ダラー』 手嶋龍一著作。第二次世界大戦の際、カウナス(リトアニア)の日本領事代理・杉原千畝が発給した「命のビザ」によって救われたあるポーランド系ユダヤ人難民「スギハラ・サバイバル」から物語は始まる。彼がアメリカに逃れ、作り出した金融先物商品「S&P 500」。1987年のブラック・マンデーは、ニューヨークから始まったと言われるが、東京と香港で前の週からパニック売りが始まっている。2001年9.11同時多発テロ事件。2008年リーマンショック。相場を大暴落させる事件を察知しているかのように、事前に金融先物商品を売り、巨額の富を得ているものがいる。北朝鮮とシリア、ミヤンマ―と北朝鮮の関係に関するインテリジェンス情報。虚実あい混ぜて物語がダイナミックに展開。ポーランドの古都・クラコフから物語が始まり、チャルトリスキ美術館の「白貂を抱く貴婦人」、「若い男の肖像」の話も出てくる。手嶋氏へのインタビュー記事が日経ビジネスonlineに掲載。 (新潮社)

『交渉術』 佐藤優著作。外交官時代インテリジェンス業務に従事し、世界の第一線で、また日本政治の中枢で活躍した著者が、現場で鍛え抜かれた「交渉術」の理論と実践を語る。交渉術の実用書として、インテリジェンスの世界を垣間見る読み物として、命がけで取り組んだ北方領土の交渉の記録として、お薦めの書。また、腐敗した外務官僚の生態について興味ある人にもお薦め。日本人は政治家の底力を軽視する傾向があるが、政治家の能力は、その国の国民の平均水準から著しく乖離することはない。日本の内閣総理大臣の能力と見識、人間性を等身大で見てほしいと、橋本、小渕、森の歴代首相たちが登場。マスコミにこき下ろされていた鈴木宗男氏への認識も百八十度変わってくる。マスコミの情報操作は恐ろしい。 (文芸春秋)

『あんぽん』 佐野眞一著作。「あんぽん」とは、「安本」の音読み。孫正義が日本に帰化する前の苗字が、安本。子供の時、「あんぽん」と言われることをひどく嫌っていた。あんぽんの語感が、「あんぽんたん」という侮蔑語につながるだけではなく、「あんぽん」という韓国風の発音が、自分の出自を隠して生きてきた孫の自尊心を深く傷つけたから。久留米大付設高校を中退し、アメリカに留学。大学在学中に自動翻訳機を発明。発明を商品化するだけではなく、その商品をいかに売るかというところまで考え、大学時代からビジネスマンであった。日本国籍取得では、苦労をして父方の韓国姓「孫」を取得。劣悪な環境の中をたくましく生き抜いた祖母。気が短くて切れやすい強烈な個性の父親。そんな夫を適当に泳がす存在感のある母親。東日本大震災の被災者に百億円の義捐金をポンとだし、10億円のポケットマネーを供出して自然エネルギー財団設立を表明した孫正義。彼のような特異な経営者がなぜ生まれたのか。朝鮮半島につながる血のルーツにまで遡り描かれる。 (小学館)

『東電OL殺人事件』 佐野眞一著作。1997年3月8日深夜、渋谷区円山町の古ぼけたアパートの一室で、女性が絞殺された。被害者渡邊泰子は、昼間は東電のエリートOL、夜は売春婦という2つの顔を持っていた。逮捕されたのは、現場の隣のビルに住んでいたネパール人、ゴビンダ・プラサド・マイナリ。この部屋のカギを預かっていたこと、以前にこの女性を買春していたことなどから、事件発生の約2カ月後に強盗殺人容疑で逮捕される。著者は、事件にかかわりのある土地に足繁く通い、被疑者ゴビンダが無実であることを確信。無実の証言を求めてネパールにまで取材。本書は、事件の発端から2000年4月の一審で無罪判決が言い渡されるまでの3年間を、泰子の心の闇にスポットをあてながら、一部始終追ったもの。 (新潮社)
(その後、警察や検察の証拠隠し、隠蔽(いんぺい)体質が元凶の冤罪事件として、人々に記憶されることになる。)

『赤い指』 東野圭吾著作。初めて読んだ彼の作品。ミステリー小説なのに心理描写が素晴らしい。中学生である息子・直巳の少女殺し。「親が悪いんだ」と、自分の犯罪を人のせいにする。その母親・八重子の息子に対する異常なバランスを欠いた愛情。息子の言うがままにしてあげることが親の愛情だと思っている。一方、義母に対する心を閉ざした冷淡な対応。そんな妻に対して、何も自分の意見を言えない夫・昭夫。そして妻にひきずられて、老いた母親にとる冷たい態度。老母・政恵のわが子・昭夫に対する深い愛情には、涙が出る。 (講談社)

『さまよう刃』 東野圭吾著作。長峰の1人娘・絵摩の死体が荒川から発見された。花火大会の帰り、不良少年グループに蹂躙された末の遺棄だった。謎の密告電話によって犯人を知った長峰。娘の凌辱されている映像を見て、突き動かされるように犯人の1人・アツヤを殺害。もう一人の犯人・カイジを追って逃走を続ける長峰。それを追う警察。正義とは何か。「少年法は被害者の為にあるわけでも、犯罪防止のためにあるわけでもない。少年は過ちを犯すという前提のもと、そんな彼らを救済するために存在する。そこには被害者の悲しみや悔しさは反映されていない。」未成年を裁く少年法は、これでいいのか。被害者の父の悲しすぎる結末。復讐すること以外に彼の生きる道はなかったのだろうか。 (角川文庫)

『手紙』 東野圭吾著作。強盗殺人の罪で服役中の兄・剛志。弟・直貴のもとには月に一度、手紙が届く。しかし、進学、恋愛、就職と、直貴が幸せをつかもうとするたびに、「強盗殺人犯の弟」という運命が立ちはだかる。不当な差別を受け、苦しむ弟・直貴。幼い娘を「殺人犯の姪」という差別から守るため、今後一切兄とは関わりを持たず、これまでの過去もすべて抹消し、今後も何の関係もないと思って欲しいと、兄への絶縁状を送る。最終章は涙が出て止まらない。直貴は、兄を切り捨てることはできない....のでは。「人には繋がりがあり、それを無断で断ち切ることなど誰もしてはならない。殺人は絶対にしてはならない。自殺もまた自分を殺すことであり、悪である。兄・剛志は社会的な死を選んだ。しかしそれによって残された弟がどんなに苦しむかを考えなかった。弟・直貴が受けている苦難も、兄の犯した罪の刑である」と言う社長。犯罪者の弟の視点に立って書かれた作品。 (文春文庫)

『容疑者Xの献身』 東野圭吾著作。天才数学者でありながら、さえない高校教師に甘んじる石神は、アパートの隣人で弁当屋に勤める花岡靖子を密かに思っていた。靖子と娘が前夫を殺害してしまったと知った彼は、愛した女を守るため完全犯罪を目論む。男が愛のためにどんなに大きな犠牲を払ったか。石神の仕掛けたトリックとは。2006年第134回直木賞受賞、並びに第6回本格ミステリ大賞を受賞し、人気作家の仲間入りを果たした作品。物理学者・湯川学のガリレオシリーズ第三作。 (文春文庫)

『医学常識はウソだらけ』 三石巌著作。95歳で天寿を全うした物理学者の語る分子栄養学・三石理論。分子生物学に基づいて、生命現象のすべてを握る遺伝子DNAから病気の予防を考える。自分の健康は自分で管理。そのために必要なのは、正しい知識。治療の方向性を間違えば、命とりになりかねない高血圧、糖尿病、心疾患といった成人病に対する「医学常識のウソ」について語る。大切なのは、細胞を作る材料であるタンパク質の摂取。ビタミンは、補助的にタンパク質を作る上で重要なもの。 (祥伝社黄金文庫)

『悪党 小沢一郎に仕えて』 石川知祐著作。元小沢一郎秘書が、「悪党」小沢一郎について語る。秘書時代の2010年1月、陸山会事件で政治資金規正法違反で逮捕・起訴され、2013年3月、東京高裁二審判決においても有罪となる。現在、控訴中。多くの人は、検察や大手メディアの反小沢キャペーンのため、小沢氏はカネに汚れた悪徳政治家だと捉えている。だが小沢氏を稀代の政治家だと信じている人も多い。政治になるとすばらしい力を発揮する人だが、普段の小沢氏は、ものぐさで、ぶっきらぼう。喜怒哀楽がはっきりしており、贅沢をしない。言い訳をしない。一郎の秘書であったがために、検察の一郎逮捕への「階段」として、逮捕・起訴された石川氏の描く小沢一郎の姿。 (朝日新聞出版)

『選ぶ力』 五木寛之著作。帯に書かれている言葉は、「人生とは選択の連続である」
日常生活の中でのささやかな選択もあれば、考えに考えた末、迷いながらも、人生を賭けて決断する難しい選択もある。「生きる」とは「選ぶ」こと。五木哲学が書かれている。 (文春新書)

『古事記 増補新版』 1980年出版・梅原猛翻訳『古事記』に 2012年「古事記論」を増補。2012年は古事記編纂が完成されてから1300年の節目になる。古事記には日本古代の歴史、言葉、思想、宗教を知る手がかりが豊かに含まれていて、古代日本の伝承を基にして詩と散文で作られた見事な文学。「原古事記」には柿本人麻呂もかかわっていたのでは?編集者稗田阿礼は藤原不比等だったのでは?