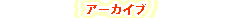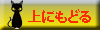vaccination (予防接種)
1798年、イギリスの医師エドワード・ジェンナーは、牛痘ワクチンを人間の天然痘予防のために種痘(しゅとう)する。vaccination(「牛」を意味するラテン語vaccaより)の命名は、最初のワクチン(vaccine)が牛に感染する牛痘ウイルスであったことに由来。ウシの病気である牛痘(人間も罹患するが、瘢痕も残らず軽度で済む)にかかった者は天然痘に罹患しない。エドワード・ジェンナーは、その事実に注目し天然痘ワクチンを開発。天然痘の予防に大いに役だつ。天然痘は非常に強い感染力、致死率(感染した人の20%から30%は死亡)、仮に治癒しても”あばた”を残すことから、世界中で不治、悪魔の病気と昔から恐れられてきた代表的な感染症。
予防接種の先駆けとして、17世紀のインドおよび中国で天然痘に感染した人のかさぶたを粉末状にしたものを病気の予防に使用したという例がある。日本では、現在の福岡県にあった秋月藩の藩医である緒方春朔が、ジェンナーの牛痘法成功にさかのぼること6年前の寛政4年(1792年)に秋月の大庄屋・天野甚左衛門の子供たちに人痘種痘法を施し成功させている。
Anglophile, Anglophobe
「銀座にアングロファイルという仕立て屋があるのよ。英国びいきと言う意味の。瀧澤局長は、そのアングロファイルなのよ」という言葉が、『ウルトラ・ダラー』に出てくる。アングロファイルとは、英語のAnglophile。-phileは、愛好家を意味する接尾辞。-philと同じ。bibliophileは、本の好きな人。また、philosophyは哲学(知を愛すること)を意味する。
アングロフォウブ(Anglophobe)とは、”イギリス嫌いの人”であり、アングロフォビア(Anglophobia)とは、イギリス恐怖症を意味する。ギリシャ語からきている。
dynabook
東芝のノートパソコンにつけられたブランド名。パーソナル・コンピュータが登場する以前、1970年代、コンピュータ科学者であるアラン・ケイ(Alan Curtis Kay)が、理想の小型コンピュータの概念モデルとして『DynaBook』構想を提唱。後に『Dynabook』と改める。将来のコンピュータとして、「GUI(Graphical User Interface)を搭載した、A4サイズ程度の片手で持てる小型コンピュータで、子供に与えても問題ない低価格なもの。文字、映像、音声等のマルチメディア対応を想定。OSはエンドユーザが理解できる均一なルール(メッセージング)と要素(オブジェクト)で構成され、このシステム自体をもユーザが自由な発想で再定義できる柔軟性や可塑性を持ちあわせている」という理想のマシンを描く。東芝では、創造的人間の理想のツールとして、『DynaBook』を目指し、名付けたそうです。日本では雑誌のアスキー社が既にこの商標登録をしていた為、アスキー社から商標権を購入。アメリカでは商標登録が認められておらず、別のブランド名を使っている。2003年、『dynabook』 のロゴに改める。 dyna-, dynam-は、「力・動力(power)」などの意の連結形。ギリシア語からきている。仲間言葉に、dynamic(動的な、力強い)、dynamite、dynamo(発電機)、 dynasty(王朝)などがある。
navigation
初めてのホームページ作成にあたり、その題を何にするかを考えた。Webだから、流行(はやり)言葉「ナビゲーション」をつけることに。そして短くナビとすることに。「navigation」って、海だとか、船との関連から生まれた言葉だろうなと漠然と思っていたけれど、この度、もっと正確に言葉の由来を知りたいと思い調べてみた。
英和辞典によれば、「navigation」は、航海、航行、運行指示と訳されている。navigateはその動詞。仲間言葉では、navy(海軍)がある。羅和辞典によれば、naviがつく言葉に、navis(船)、navigare(航海する)、navigator(航海者、水夫)とある。navigateもnavyも船からきている言葉である。
WEDGE
株式会社ウェッジの発行する総合月刊誌の名前。新幹線のグリーン車に乗れば、無料配布だそうだ。購読する場合は、定価¥400で、JRや私鉄・地下鉄の売店、書店で購入できる。購読者として、政界財界のリーダー、企業の経営者など組織のトップ、役員・部長など組織内において意思決定権を持つ人、富裕層、スポーツ・芸能関係者のようなトレンドリーダ達に、照準をあてている。ふーん、そうなの。私はすべての照準から外れているけれど、書かれた記事は中々面白い。WEDGE Infinityに、辛坊氏のヨット遭難記事が出ている。私は彼のことを誤解していたようだ。wedgeとは、楔(くさび)のこと。
たらいの水
「たらいの水」とは、水を自分の方に寄せようとすれば、水は逃げていくが、相手の方に水をあげようとすれば自分の方に返ってくる。お金で言うと、自分だけ儲けようとしても儲からない。 まず相手を利することによって、結果として自分も利益を得る、という 訓話。他チームのリーダが成果を自分の手柄にすることが少なくない中で、「たらいの水」の話を聞いていた女性が、「たらいの水」に倣って、チームの成果をすべて部下の手柄にした。するとチームが活気づき成績も上がったというわけ。雑誌WEDGEに載っていた。「たらいの水の原理、あるいは哲学」と言われているそうです。