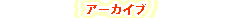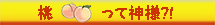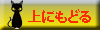今どき『古事記』・もう一度『古事記』 ― 雑記
『古事記』(現代語訳)を読んでいると、私たちの慣れ親しんだ地名が出てくる。日本列島の誕生の際、最初に生まれたのが淡路島。四国は伊予と呼ばれており、讃岐、伊予(えひめ)、土佐、粟と四つに分かれていた。3番目に隠岐が誕生。九州は筑紫の島と呼ばれており、筑紫の国、豊国、肥の国、熊曾の国と4つに分かれていた。5番目に伊岐。6番目に対馬。7番目に佐渡。そして8番目に豊秋津島と呼ばれる本州が誕生。この名前にはなじみがなく、大八島の国という呼び名と同様、『古事記』でしか知られていない。小豆島は、古代では「あずきじま」と呼ばれていた。大きい島なのに、何故その他の6島の中の一つなのか?隠岐や壱岐、対馬は、古代では重要な役割をはたしていたのだろう。北海道が出てこないのは、当時、その島の存在を認識していなかったということなのか。その他の6島はすべて瀬戸内海に浮かぶ島々ではないかと思ったのだけれど、ある説によると、九州の五島列島が含められている。古代の人々は、陸路よりも海路(瀬戸内海)を利用していたと思われる。応神天皇が皇踏山(小豆島)に登ったとか、神功皇后の船が新羅遠征の時、島の沖を通っていったとか、言い伝えがある。
『古事記』を検索すると、随分たくさんの人がブログやホームページで書いている。解釈もいろいろあるようだ。伊耶那岐の漢字も本によっては、伊邪那岐となっているし、大神が祭られているのは、近江の多賀神社ではなく、淡路島の多賀神社とする説もある。
伊耶那岐命は、黄泉の国から地上へ逃げ帰る途中、桃の呪力によって助けられ、桃に意富加牟豆美命(おおかむづみのみこと)という名を賜わる。これは大いなる神のミ(霊威)という意味。
桃は中国では仙木とも呼ばれ、邪気を払う呪力があると考えられていた。日本でも桃は不思議な霊力があると信じられており、ひな祭りは、桃の節句と呼ばれ、桃の花を飾り、桃酒を飲んで、桃に災厄を払ってくださいということ。
桃太郎伝説もこの桃の呪力の信仰から生まれたもののようだ。
リンゴが西洋を象徴する果物であれば、桃は東洋を象徴する果物と言える。