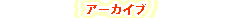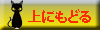今どき『古事記』・もう一度『古事記』 ― 国生み
大八島(おおやしま)の国
伊耶那岐命(いざなぎのみこと)と伊耶那美命(いざなみのみこと)の二柱の神は、天(あま)つ神たちに、「このただよって不完全な国を整えて完成してほしい」と命じられる。天の沼矛(あめのぬほこ)を与えられた伊耶那岐、伊耶那美は、天上と地上をつなぐ天の浮橋に立って、その沼矛を降ろしてかき回し、その矛を引き上げたとき、その矛の先からしたたり落ちた塩がかさなって島となった。それが淤能碁呂島(おのごろしま)である。
その島にお降りになり、お生みになった子が、淡路島。つぎに伊予の男女の名を持った島(四国))をお生みになった。この島は身体が一つで、顔が四つある。一つの顔ごとに名がある。伊予の国を愛比売(えひめ)といい、讃岐の国を飯依比古(いいよりひこ)といい、粟の国を大宜都比売(おおげつひめ)といい、土佐の国を建依別(たけよりわけ)という。つぎに、隠岐(おき)の三児(みつご)の島をお生みになった。別名、天之忍許呂別(あめのおしころわけ)という。つぎに筑紫(九州)の島をお生みになった。身体が一つで4つの顔があり、その顔ごとに名前をもっている。筑紫の国を白比別(しらひわけ)といい、豊国(とよくに)を豊日別(とよひわけ)といい、肥の国を建日向日豊久士北泥別(たけひむかひとよくじひねわけ)といい、熊曾の国を建日別(たけひわけ)という。つぎに伊岐の島をお生みになった。またの名を天比登都柱(あめひとつばしら)という。つぎに対馬をお生みになった。またの名を天之狭手依比売(あめのさでよりひめ)という。つぎに佐渡の島をお生みになった。つぎに大倭豊秋津島(おおやまととよあきつしま=本州)をお生みになった。またの名を天之御虚空豊秋津根分(あめのみそらとよあきつねわけ)という。これら八つの島をお生みになったので、この国を大八島の国という。
こうして二柱の神は大八島の国以外にも吉備の児島、小豆島(あづきじま)、大島、女島(ひめじま)、知訶島(ちかのしま)、両児島(ふたごのしま)の6島をお生みになる。その後、山の神、海の神、風の神など多くの神をお生みになるが、伊耶那美命(いざなみのみこと)は最後に火の神迦具土(かぐつち)をお生みになって、女陰を焼かれて亡くなられた。
黄泉(よみ)の国
伊耶那岐は、妻の伊耶那美を追って黄泉の国へ行くが、伊耶那美の変わり果てた姿をみて恐ろしくなり逃げ帰る。途中黄泉の国の者たちに追われるが、黄泉の国の急な坂の麓に着いたとき、そこにあった桃の木から実を三つ取り、坂の上で待ち構えて撃つと、桃の呪力によって、黄泉の国の者たちは、すべて坂から帰って行った。それゆえ、伊耶那岐命は桃の実に、「お前は、わたしを助けたように、この葦原の中つ国にいる、あらゆる生きている人間たちが苦しいことに出会って、憂い悩むとき、助けてほしい」とおっしゃって、桃に意富加牟豆美命(おおかむづみのみこと)という名を賜った。
とうとう、妻の伊耶那美本人が追いかけて来た。そこで、伊耶那岐命は千人引きの大きな石を、その黄泉の国の急な坂に置いて、その石を中にして、伊耶那美命と対面して、離婚をいいわたす。
そのときに、伊耶那美命は、「愛しいあなたが離婚なさるのなら、わたしはあなたの国の人間を一日千人絞め殺してしまいましょう」とおっしゃった。そこで伊耶那岐命は、「愛しいわたしの妻よ。お前がそんなことをするなら、わたしは一日に千五百人の子を生ませよう」とおっしゃった。
こういうわけで、この世では、一日に必ず千人が死に、千五百人が生まれるのである。そこで伊耶那美命を名付けて、黄泉都大神(よもつおおかみ)といい、また、追いついたことにより、道敷(ちしき)の大神という。また黄泉の国の坂を塞(ふさ)いだ石は、道を引き返させた大神といい、黄泉の国を塞ぐ戸の大神ともいう。なお、その黄泉津比良坂(よもつひらさか)というのは、いまの出雲の国の伊賦夜坂(いふやざか)である。
みそぎの神々、天照大御神、須佐之男命
黄泉の国からやっと帰られた伊耶那岐大神は、「わたしは、とても醜い汚い国に行っていたので、みそぎをしなければならない」とおっしゃって、筑紫の日向(ひむか)の橘(たちばな)の小さな水門(みなと)の阿波岐原(あわぎはら)へやって来て、みそぎをされた。その時に、身につけていたもの(杖・帯・袋・上着・袴・冠・腕輪)を投げ捨てる時に十二柱の神々がお生まれになった。そして、「水面は水の流れが速く、水底はおそい。」とおっしゃられて、海の真ん中で身体(からだ)を洗われた時、黄泉の国の汚物による神々、その禍を直そうとする神々がお生まれになる。つぎに海底、海中、海面でみそぎをなさったときに三柱の綿津見神(わたつみのかみ)がお生まれになる。また底筒之男命(そこつつのおのみこと)、中筒之男命(なかつつのおのみこと)、上筒之男命(うわつつのおのみこと)の三柱の神がお生まれになり、これらは住吉大社に祭られている三座の大神である。綿津見神は安曇之連(あずみのむらじ)たちが祖先神としてお祭りしている神である。
ここで、伊耶那岐大神が左の目を洗ってお生まれになった神の名は天照大御神。つぎに、右の目を洗ってお生まれになった神の名は月読命(つくよみのみこと)。つぎに鼻を洗ってお生まれになった神の名は建速須佐之男命(たけはやすさのおのみこと)である。この三柱の神がお生まれになったので、「多くの子を生んで、最後に3人の尊い子を持つことができた」とお喜びになり、天照大御神には、高天の原を、月読命には、夜の国を、須佐之男命には、海原の支配をお任せになった。
それぞれの神は、伊耶那岐命の命じた国を、それぞれ治められたが、須佐之男命だけは、海原の統治をなされずに、あごひげがのび、胸に達するほどの長い間、ひどく泣き悲しんでおられた。その泣く様子は、青山も枯山になり、川や海もすっかり涙となって乾いてしまうほどであった。このために、悪い神様のしわざが5月の蠅(はえ)のようにうるさく起こり、あらゆる災いが起こった。
そこで、伊耶那岐大御神は、須佐之男命に、「どういうわけで、命じた国を治めないで、泣きさわいでいるのだ」と聞くと、須佐之男命は、「わたしはお母さんのいるあの根の国に行きたくて泣いているのです」とお答えになった。伊邪那岐大御神は大変お怒りになり、「お前はこの国に住んではいけない」とおっしゃって、須佐之男命を追い払ってしまった。
伊邪那岐大神は今は近江の多賀神社にお祭りされている。 (参考文献:梅原猛『古事記』)