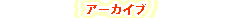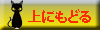今どき『古事記』・もう一度『古事記』
先日新聞を読んでいると、今、漫画の『古事記』が人気があるらしい。その数日後、新聞の広告欄に漫画『ヤマトタケル』の広告が載っていた。やはり『古事記』ブームなのか?聞くところによると、一般書物の『古事記』も人気があるらしい。何故、いまどき『古事記』なの?私の方は、梅原猛の『古事記』が出版されていることを知り、予約待ちでかなり待たされ、やっと図書館で借りてきて、読み終えたところ。以前から『古事記』の知識は漠然としていて、『古事記』といえば、昔、子供のときに映画でみた『日本誕生』の知識くらいで、それも随分昔々の話なので、断片的な記憶でしか残っていない。天照大神(あまてらすおおみかみ)が天の岩戸に隠れるシーン、須佐之男命(すさのおのみこと)の八岐大蛇(やまたのおろち)の退治シーン、そして倭建命(やまとたけるのみこと)の東国征伐どきの草原での火に囲まれるシーンなど、よくその内容が分かっていなかった。なんせ今回この『古事記』を読むまでは、須佐之男命と倭建命が同じ人物だとずっと思っていたくらいだから。そして今、何故そんな誤解をしていたのかがよく分かった。主役・三船敏郎が須佐之男命と倭健命の二役をしていたためなのです。
映画『日本誕生』は、1959年10月公開。映画通の話によれば、監督稲垣浩は巨匠に数えられる名監督だし、脚本家八住利雄や菊島隆三も名脚本家と言われている。東宝映画1,000本目の記念作品として、豪華キャストで制作された映画です。
以下、梅原猛の『古事記』の中の『古事記に学ぶ』より抜粋です。
『古事記』には、序文がついていて、太安万侶(おおのやすまろ)が、ときの天皇元明天皇の命(めい)を受けて、711年9月18日に編纂(へんさん)を開始し、翌年(712)正月28日にそれが成ったことが書かれてある。そこには天地創造から推古天皇までの国の歴史が書かれている。
『古事記』というのは、文字通りフルコトブミであり、古代史といってよいのかもしれない。『日本書紀』に比べて『古事記』の方が正確に日本古代のことを叙述しているところがある。8世紀以前の日本の歴史を知るには、もっとも多くこの書によらねばならない。
また、この書には、古い日本の言葉が保存されている。ただ7、8世紀の日本の言葉のみではなく、特に歌謡などには、当時すでにその意味も定かにわからなくなっていた言葉が含まれている。
この点においても、『古事記』は『万葉集』とともに、日本古代語の宝庫であり、われわれ日本人の、あるいは日本文化の根源を窮(きわ)めるためには、このような言葉の研究が不可欠になる。
思想は言葉を離れてはありえない。したがって、日本古代の思想の研究は、古い言葉の研究なくしてはありえないが、本居宣長(もとおりのりなが)が堅く信じていたように、『古事記』の中には、『万葉集』以上に古い日本人の思想が含まれている。
『古事記』の作られた和銅5年(712)という年は、政治的に重要な意味を持った年である。『古事記』の編纂という事業は、藤原不比等による律令国家建設のさ中に起こった出来事なのである。
この律令国家の建設の仕事は聖徳太子と蘇我馬子によって始められたが、天智天皇と藤原鎌足によって敢行(かんこう)された大化の改新によって、はっきりした国の方針になった。
その仕事を天智天皇の皇女に当たる元明帝を天皇に仰いで、鎌足の息子の不比等が完成したわけであるが、彼はまず、大宝元年(701)に、わが国初めての完備した律令である大宝律令を作り、和銅元年(708)、わが国初めての公式紙幣である和銅開宝をつくり、和銅3年(710)にわが国初めての計画的首都奈良への遷都を敢行した。『古事記』撰修の命が出たのは、この遷都の翌年の9月18日であり、そしてそれが完成したのは、翌々年の1月18日である。そしてそれから8年後に『日本書紀』が作られた。そして、その年、不比等は死んだ。
不比等がほぼ権力を手中に収めたのは大宝元年のことであり、和銅元年には不比等は独裁的権力をにぎった。『古事記』も『日本書紀』も、この不比等の独裁の期間にできたものである。