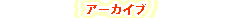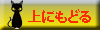日付: 2014/10-12
デイビッド・ギャレット(David Garrett)、 ”Who is the real you?" (その1)
9月上旬、パガニーニの映画を観て以来、主役を演じたデイビッド ギャレットを毎日ネットで見ない日はないほど、彼の魅力にとりこまれてしまった。デイビッドは、欧米にてバイオリニストとして有名なだけではなく、クラッシックと現代音楽ロックやポップスを結びつけたクロスオーバー・ミュージックなるものを展開していて、今や知る人ぞ知るスーパースターでありました。(Googleでの検索は16,000,000件をヒット!)私のお気に入り欄は、彼の演奏やインタビューの映像、記事、彼の崇拝者のブログで溢れてしまって、整理不能状態。今までロックやポップスなんて言われても、違いも分からず、全く興味が湧かなかった私ですが、彼の奏でる音色なら、ロックも聴いてみようかなと思い始めている。バイオリンの音色がこんなに美しいなんて、もっと早く気づきたかった。このひと月、時間を見つけては、インターネットでデイビッドにアクセス。音楽をかけたり情報検索をしていると、時間の経つのが速く、気付けば夜中の12時を既に回っている。最近、睡眠不足気味で、背中は痛く、目は痛く。
「パガニーニ 愛と狂気のバイオリニスト」の映画の中で最も美しい印象的なシーン: デイビッド・ギャレット・パガニーニの奏でるバイオリンの美しく切ない音色、ピッツイカートに合わせて歌われる美しいアリア、そのあとのシャーロットの静かにパガニーニに問いかける言葉:
これはギャレットのパガニーニだ。バイオリンを弾くその立ち姿の美しいこと。美しくひびき渡る彼自身の音色。デイビッド・ギャレットって何者なの?ニコロ・パガニーニではなく、本当のギャレット自身ってどんな人なの?俄然興味が湧きあがった。
デイビッド・ギャレット(David Garrett)、 ”Who is the real you?" (その2)
読みかけの本が気になり、2~3日デイビッドから離れていた。本は読み終えたし、気持ちが落ち着いたところで、さあ、デイビッドに集中だ。
デイビッド・ギャレットは、1980年9月4日、ドイツ西部アーヘン(Aachen)にて、ドイツ人弁護士の父とアメリカ人バレリーナの母との間に生まれる。ダーフィット・ボンガルツ(David Bongartz)が本名。母親(スコットランド系アメリカ人)の旧姓がGarrettであり、それをconcert nameとして使っている。 4歳の時、2歳上のお兄ちゃん(Alexander)がバイオリンを習い始め、兄の持っているものは何でも欲しがる弟は、自分も同じようにバイオリンをあてがってもらい、弾き始めた。上達がとても速いデイビッドに、お父さんは音楽の才能を見出す。5歳の時、地方のコンペで優勝し、13歳までには、ズービン・メータやクラウディオ・アバドのような指揮者と仕事をし、14歳でドイツ・グラモフォン社とレコード契約を結び、17歳までに、モーツアルト、パガニーニ、ベートーベン、バッハ等のレコードを出す。
10歳で既に神童と呼ばれ、拍手喝采、驚嘆され沢山のお金も得たけれど、友達はいなかった。8歳の時に両親は彼を学校から連れ出し、それ以来舞台から舞台へと演奏の旅をしているため、同世代の子供たちと行動を共にする機会もなく、孤独で寂しい子供時代を送り、とても悲しかったと語っている。誕生日には父親と二人でホテルでお祝いをしていた。
15~16歳の時、左腕に問題が生じるが、誰にも言えず、ひどい痛みを抱えたまま、みじめな気持ちで舞台に立っていた。病院に行くべきだと両親に訴えても、バレーリーナだった母親は、とても強い精神力の人(tough cookie)で、気力が足りない("Mind over matter")と言う。3年程経った17歳の時、1人で医者に行く。同じ姿勢で長時間練習を繰り返してきた為、肩や首、腕のあちこちに腱炎が広がっていた。21歳頃までその痛みは続く。今では、毎日の練習を短時間で何回か繰り返す方法に変え、またジムに行ったりしたおかげで(hit the gym)、痛みはなくなった。
少年時代の彼の苦悩が一部語られているビデオがYouTubeにあり。その中にアイザック・スターン(Isaac Stern)とのレッスン風景(1995年)がある。デイビッドはスターン氏の自分への態度に疑問を持ち、「他の人達にはとても優しいのに、何故自分には批判的でいつもそんなに厳しいのですか」と尋ねる。「他の人のことは気にならない」という最高の褒め言葉をもらう。「二人だけで話をしよう。お父さんは連れて来ないで」と言われ、長い会話をした。「自分自身を見つけなさい。自分の声を見つけなさい。個性を持ちなさい」とアドバイスをうける。”両親の元を離れなさいと言われたわけではないけれど、家にいたのでは、そんなことはできないことが分かっていた”と語っている。多感な青少年時代を迎え、両親の元を離れ、自分探しをしたいと考え始めるひとこまだったのかもしれない。そのビデオがこれ↓
彼は、20世紀最高の演奏者である、イダ・ヘンデル(Ida Haendel)、アイザック・スターン、ユディ・メニュイン(Yehudi Menuhin)、イツアーク・パールマン(Itzhak Perlman)達のレッスンを受ける。彼は子供の時から、直接イダ・ヘンデルのレッスンを受けるため、ロンドンまで足を運んでいる。イダは、彼女のやり方を真似るのではなく、彼女の演奏をしっかり聞いて、デイビッドが感じることを演奏しなさいと言い、お互い何度も演奏し、聴きあう。彼女にとって、好きであるとか、好きでないとかは、問題でなく、デイビッドが自分自身で考えることがとても大切なのだと。
18歳の時、彼はジュリアード音学院のイツアーク・パールマンに教わるため、ニューヨークへ移る決心をする。もちろん、両親の許しはもらえない。一方的な決意である。ということで、いよいよ、デイビッド旅立ちの時を迎える。
彼の演奏するクラッシックのビデオあり。↓
デイビッド・ギャレット(David Garrett)、 ”Who is the real you?" (その3)
両親の猛反対を押し切り、彼らに気づかれないように、こっそり、ニューヨークに飛び立ったデイビッド。親からの援助は得られず、1人でのニューヨーク生活が始まった。それまで両親やマネージャーがすべて面倒を見てくれていたので、銀行に行ったことすらなかった。銀行口座は持っているのか、どこで買い物をしたらいいのか、英語はできても、新しい自立生活は楽ではなかったようだ。だが、子供の時は舞台に出てヴァイオリンを弾く小さなコンピュータみたいで実体がないと感じていたデイビッドにとって、ようやく自分の人生を自分でコントロールできる生き方は素晴らしかった。生活費、学費を稼ぐために、地下鉄で演奏したり、レストランのバスボーイ(食器を片付けたり、リネン類のセッティングをする業務)をしたりした時期もあったらしい。割のいいモデルのバイトをやっていたのは、この学生時代である。
かなり長い間、先生なしで来たため、ヴァイオリンの弾き方を再調整していた。もちろん、イダ・ヘンデルに師事してはいたが、規則的に会っていたわけではなかったし。だからジュリアード音楽院に入学した時、弓と腕の動かし方、ソロイストとしての音の出し方、そのための正しい姿勢のとり方等、殆どパールマンから教わった。大学では、音楽理論と作曲を学び、2003年、バッハ風フーガでジュリアードの作曲コンペにて優勝。
ジュリアードにて、初めて同世代の人達との結びつきができ、同世代の仲間が何を聴きたいのかがよく分った。2002年か2003年の時、アントワープにてクロスオーバー・イベントがあり、デイビッドはクラッシック演奏者として参加。クラッシックを概して聴かない聴衆を前に、ベートーベンやサンサーンスを弾き、その夜受けた熱狂に目を開かされる。クラッシックは誰の心にも結びついている。クラッシック音楽そのものに問題があるのではなく、それが提供される環境や方法に問題があるのだ。問題はその持って行き方である。
デイビッドのプログラムが開始する。素晴らしいクラッシックを多くの人達に聞いてもらう為に。

2014年10月26日、レコード「DAVID GARRETT Garrett vs Paganini」で、ECHOクラッシック2014・ベストセラーを受賞。受賞時に演奏されているのが、パガニーニの「ヴァイオリン協奏曲第4番 ニ短調~第2楽章」をデイビッドがアリアとして編曲した、"Io Ti Penso Amore"。その映像がこちら↓。始まって4秒あたり、4分44秒あたりに映るのは彼のご両親。
このレコードのなかには、タルティーニ(Giuseppe Tartini)の「悪魔のトリル(Devil's Trill Sonata)」も含まれている。↓
デイビッド・ギャレット(David Garrett)、 ”Who is the real you?" (その4 - 最終)
先日、「題名のない音楽会」を聴いていると、出演していた3人のバイオリニストが最後に、モンティ(V.Monti)のチャールダーシュ(Czardasz)を弾いた。この曲はデイビッドの演奏でよく耳にしている曲なので、とても興味深く、耳を澄まして聴いていると、演奏者によって音色が全然違っていることを実感。当たり前のことなんでしょうが、「自分の音を持ちなさい」って、このことなんだ。デイビッドの音は、力強く透き通っていて、気品がある。弾き方も美しい。2007年6月にアップロードされたYoutubeから。↓
そして2007年、技術力の高い洗練されたクロスオーバー・アルバムで一躍世界に躍り出たデイビッド。

2007年2月、デイビッド自身が初めてプロデュースし、初めてのクロスオーバー・アルバムとなる「Free」がリリースされる。最初の試みで、Amazon売上チャート第一位に躍り出る。



2008年3月、曲を少し調整してリリースされたものが「Virtuoso」。”ECHO Classic 2008 Classic Without Borders"を受賞。
だがそれに至る迄の道のりは、そう簡単ではなかったようだ。親からは「時間の無駄。エネルギーを消耗するだけ。今までのクラッシック演奏者としてのキャリアを壊してしまう。」と反対され、ドイツのレコード会社からは、「そんなもの売れるはずがない。」と相手にされなかった。イギリスのDeccaレコード社にデモ版をもっていったところから、デイビッドのクロスオーバーへの道が大ブレイクしていく。
その3~4年の間、クラッシックの演奏活動もやっており、2005年はプロモーションで来日していて、サモン・プロモーションのスタッフに満面の笑顔でデモトラックを聴かせていたとか、2006年は横浜みなとみらいホールで微笑を浮かべて楽しそうに演奏していたとか。そうか、みなとみらいにも来ていたんだ。

2008年10月、「Encore」をリリース。アメリカにて”Classical and Classical Crossover”チャートにて第一位。

2009年11月、純クラッシック・アルバム「Classic Romance」をリリース。”ECHO Classic 2010 Bestseller of the Year”を受賞。


2010年6月、「Rock Symphonies」に挑戦。バロック時代から現代に至るクラッシックを新しいスタイルで演奏。”ECHO Awards 2011 Best National DVD Production ”を受賞。また”Best National Rock/Pop Artist”の部門でも受賞。



2012年、「Music」をリリース。”ECHO Awards 2013 Best National POP/Rock Artist”を受賞。

2013年10月、パガニーニの自伝映画「パガニーニ 愛と狂気のヴァイオリニスト (The Devil's Violinist)」がまず最初ドイツにて上映される。日本での上映開始は2014年7月。デイビッドの映画初出演にして、主役パガニーニを演じ、ヴァイオリン演奏、制作総指揮・音楽も担当。私が初めてデイビッド・ギャレットというクロスオーバーで大ブレイクしているバイオリニストの存在を知ったのはこの映画がきっかけ。「Garrett vs Paganini」はこの映画に鼓舞されて作られたアルバム。”ECHO Classic 2014 Bestseller of the Year”を受賞。
4歳の時にバイオリンを習い始め、父親は彼の音楽の才能に気づく。才能のある人は極めてわずかだけれど、その才能に気づかれることなく人生を終えた人も少なくないはず。恵まれた運を持って生まれてきた人である。過酷なレッスンを日々受けながらも、それにこたえ、彼の才能は開花していく。精神的な強さも相当である。また、子供の時から、世界的に有名なバイオリニストや指揮者達との出会いがあり、彼らの薫陶を受け、そこには我々の想像を超える影響を受けたと思う。人との出会いは大切。彼の場合は、その出会いが超一流の人たちばかりである。18歳の時、親の猛反対を押し切って彼独自の道を進み始める、その勇気と行動力。子供の時から磨き続け、洗練された音楽の才能があったから、前へ前へとひたすら進んでいけたのだろう。自分が今何をやりたいのか。「誰も挑戦していない技術力の高いクロスオーバーな曲を人々に届けたい。そして人々にクラッシックの素晴らしさを知ってもらいたい。」と、即、行動に移すデイビッド。「いったい自分は何をしたいのだろう?」と、ずっと目的が見つけられずに生きている人も数多くいるというのに。
デイビッドには神から与えられた使命のようなものを感じる。音楽の世界が大きく変貌しようとしている?最近クラッシックを学んだ人たちがよく街頭で演奏している姿を見たり、クロスオーバーを目指している等と話しているのを聞くと、これってデイビッドの影響?と思ってしまう。
彼は話をするのが大好きなようで、ライブではマイクを持って、よくおしゃべりしており、人を楽しませるエンタテイナーでもある。音楽の才能だけではなく、しゃべくりの才もある。企画力もあり、なんと言ってもエネルギッシュに行動できるタフな人だ。また若い時のルックスはとても可愛いし、中年に変わろうとしている今は、落ち着いた気品を感じる。人に語れない大変な苦労もあるでしょうが、神に選ばれし人だと思う。
参考文献:
Violinist.com interview with David Garrett: 'Legacy'
http://www.david-garrett.com/about
http://www.notesontheroad.com/david-garrett.html
日付: 2014/9/7(加筆修正: 2014/10/5)
パガニーニ 愛と狂気のヴァイオリニスト (The Devil's Violinist)
Bunkamuraル・シネマにて上映中(7/11~9/12)。そろそろ終盤を迎える為、9/5(金)、やっと重い腰を上げて渋谷まで出かける。一日1回上映の為か一時間半前に到着したにもかかわらず、既にほぼ満席状態。前の方の席しか取れず。キャスティング、音楽等の詳細についてはチラシを参照。
パガニーニ(Niccolo Paganini)(1782/10/27-1840/5/27)は作曲家・ヴァイオリンの超絶技巧奏者(virtuoso)として名前が知られている。豪華絢爛な映像の美しさ、主人公パガニーニを演じるデイヴィッド・ギャレット(David Garrett)(1980/9/4~)の退廃的な美しさ、周りを圧倒してしまうその存在感、そして彼自身の演奏するパガニーニの蠱惑的な美しい旋律に魅了されてしまった二時間だった。D.ギャレット(パガニーニ)のヴァイオリンに合わせて歌われるアリアが素晴らしく、ワトソン邸で初めて歌われる感動的な場面がYouTubeにあり↓
このアリアは「ヴァイオリン協奏曲第4番 ニ短調~第2楽章」をD.ギャレットがアリアとして編曲したもの。映画の中では、シャーロット役のアンドレア・デック(Andrea Deck)自身が歌っている。また、ニコール・シャージンガー(Nicole Scherzinger)という、米国のポップ系の女性シンガーソングライターも、D.ギャレットのニューアルバム 「Garrett vs. Paganini」の中で歌っている。お二人とも声が美しいだけでなく、姿形も美しい。声が似ていて最初は違いがよく分らなかったけれど、よく聞いているとニコールの声の方が、よりソフトで、のびやかだ。天使のように美しく響きわたる声、そして彼の奏でるバイオリンの音色のなんて激しく、やさしく、せつないことか。
上演時間になリ演奏を始めても姿を現さず、どこに行った?逃げてしまった!?とやきもきしていると、突然観客席の後ろから「カプリチェ24」が聞こえる。曲を奏でながら登場するパガニーニ。↓
酒場で演奏される曲は「ヴェニスの謝肉祭」↓
リストのピアノ曲で有名なメロディは、実はパガニーニのヴァイオリン協奏曲をピアノ用に編曲して作られたものであることに気づく。映画の中で使用された「ヴァイオリン協奏曲第2番 ロ短調 ~第3楽章『ラ・カンパネラ』」は、映画のシーンのものは、YouTubeに見当たらず、代わりに彼が14歳の時に弾いた時のもの。↓
原題は"The Devil's Violinist"。監督. 脚本はバーナード・ローズ(「不滅の恋 ベートーベン」を監督)。映画初出演にして、主役パガニーニを演じたデイヴィッド・ギャレットは、ヴァイオリン演奏のみならず、制作総指揮・音楽も担当している。溢れるばかりの才能の持ち主で、何ともうらやましい限りだけれど、それは凡人の思うことかもしれない。天賦の才の持ち主は、その溢れ出る才能に絶えず揺さぶられて、心も体も休まる時がないのではないだろうか?
チラシの出演者名の中に、ヘルムート・バーガーを見つける。往年の美青年は、どうなっているのだろうと、興味深々だったが、変貌していて全く分からず。最後のエンディングに出てくる配役・俳優名にて、バーガーシュ卿(Lord Burghersh)の役で出ていたことを確認。昔の面影全くなし。
9/27より同じくBunkamura ル・シネマにて『アルゲリッチ 私こそ、音楽!』が上映される予定。
エンジェルロード
この6月、一年ぶりに小豆島に帰省しました。その時撮った「エンジェルロード」です。子供の時は、よくここに潮干狩りに来たものです。また、8月15日のお盆の最後の夜は、家族で精霊舟(しょうろうぶね)を流しに来ました。子供時代を思い出す懐かしい場所です。
余り深く考えず、漠然と「余島」(よしま)と呼んでいましたが、「大余島」(おおよしま)と呼ばれる島がその奥にあります。大余島は、1950年(昭和25年)に神戸YMCAが余島野外活動センターというキャンプ場を設置して以来、同法人の私有地なのだそうです。子供の時、大余島まで行くことがなかったのはそんな事情であったのかと、今分かりました。一度だけ、大余島に用のある伯母にくっついて行った記憶があります。
干潮時には余島全島が砂州で繋がり、陸続きになり、その砂の道で潮干狩りをしました。夢中になって貝掘りしていると、いつのまにやら潮が満ちてきて砂州が海に沈んでしまいそうで、慌てて本島まで引きかえしたものです。満潮時には離れ小島となりますが、干潮時だけに現れるこの不思議な砂の道は、今では、「エンジェルロード」とおしゃれな名前で呼ばれています。潮の干満により、姿を現したり、海に消えたりと、1日に2回干潮の時のみ渡ることの出来る砂の道は、いつのまにやら「天使の散歩道」になっていました。
余島について、以下ウイキペディアより抜粋です;
余島は元々は、北から弁天島、小余島、中余島、大余島の4島の総称であった。その後弁天島は埋め立てで小豆島(前島)と陸続きになり、小余島と中余島は法定上一つの島として中余島と呼ばれるため、現在は中余島及び大余島の2島の総称になっている。余島(よしま)という名称は「四島」からきている。 また、この島々が所属する小豆郡土庄町字余島は日本郵便株式会社から交通困難地に指定されていて、直接郵便物が届かない。瀬戸内海に所在する島で交通困難地に指定されているのはこの島が唯一である。電力や水道及び固定電話は引かれている。
『あの日からの建築』
東日本大震災後、建築家・伊東豊雄氏は、近代主義による建築の在り方に疑問を持ち、もっと自然にそった減災方法や集合住宅のあり方を震災復興のために具体的に提案。以下要約。
「物事を明確に切り分ける近代主義には、、曖昧さがないが、科学技術の発展に大きく貢献した。一方、日本では、言語を始め、生活習慣、ものの考え方が、曖昧ではあるが、その曖昧さ故に日本文化を豊かに保ってきた。
建築を例にとると、近代主義思想では、機能によって内外の境界を、あるいは部屋相互を明確に隔てることで、優れた建築が生まれると信じてきた。しかし、日本の伝統的な建築は自然に対して開かれており、部屋と部屋の関係も機能によらず曖昧に連続している。
防潮堤に関しても、ラインで切り分ける考え方がすべてだとは思わない。日本建築が雨戸や格子、すだれ、障子、襖など多様な要素を用いて内外を隔てたように、もっと繊細かつ多様なマウンド(盛り土)や壁面を組み合わせて、水を遮る方法を考えるべきだと思う。今回津波で流された地域を歩くと、屋敷林や小さなマウンド、頑丈な壁の背後などで救われ無事だった住宅を幾つも見ることができた。もっと繊細な防潮の対策を講ずることは十分に可能だと思われる。」
伊東氏は、「せんだいメディアテーク」の設計者。